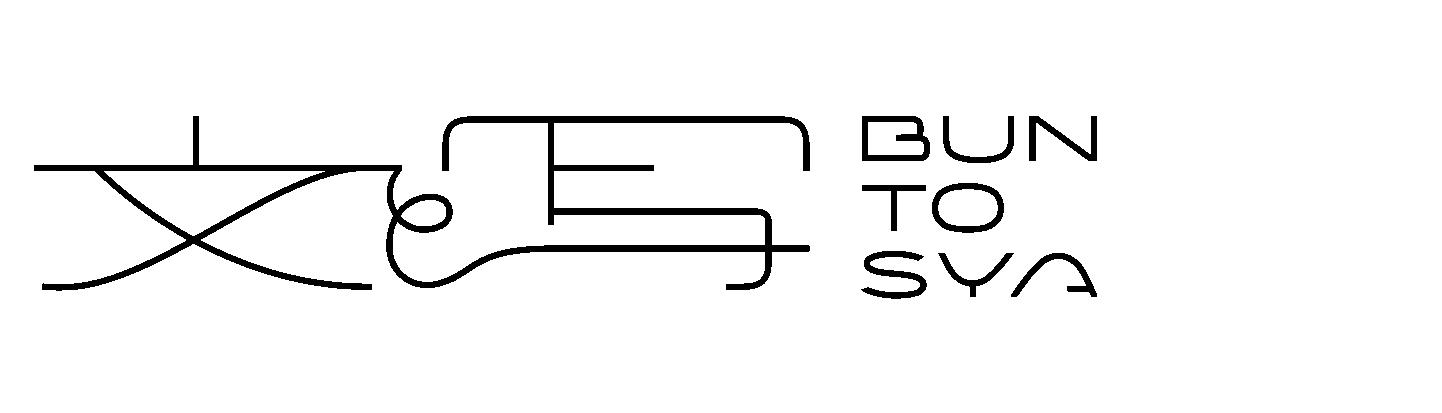小学生の長男は、YouTubeが趣味だ。
朝起きて「どうが!」から一日は始まる。顔を洗うよりも先に、iPadのスタンドを立てて机に置く。朝一番のルーティンだ。
この状況を客観的にみると、デバイスへの依存度がとても高い。7歳の子どもが朝起きてからすぐ画面に向かうのは、親として最も避けたかった生活習慣… 。せめて、見る時間を「15分まで」と息子に相談して、制限している。
そんな中、2024年11月29日、オーストラリアで16歳未満のSNS利用を禁止する法律が可決された。冒頭で紹介した、我が家の長男。いずれ年頃になれば、YouTubeを入り口としてSNSへと移行していくだろう。今後、辿りつくであろうSNSの危険性について考えてみたい。
iPadを子どもに使わせなかった、ジョブズ氏
アップル社の共同創業者のひとり、故スティーブ・ジョブズ。自分の家庭でiPadをさぞ愛用していると思いきや、子どもに対してはiPadを制限していたと語る。2010年のニューヨークタイムズで取材された記事によって明かされた。質問した記者は、ジョブズ氏の回答に驚いた。その当時、彼は4人の子どもがいた。13歳と15歳の2人には、iPadを使わせていなかったと語る。理由のひとつに「依存性への懸念」が挙げられた。商品開発の人間が普段の生活で使用していない事実は衝撃的な事実だ。
我が家のように、制限しながらデバイスと付き合う。もう一つは全く関わらない。ここでは、ふたつの触れ合い方の事例をご紹介した。子どもの教育方針、家庭によってさまざまな関わり方があるだろう。日本の小学校では、授業でタブレット端末が一人一台支給されている(一部、支給対象外の県もある)現代を生きるわたしたちがデバイスの利用を制限することは、なかなか困難な状況だ。デバイスと触れ合うことがなければ必然的に危険と向き合うリスクはないが、この時代、ほぼ不可能といえる。
子どもはSNSで危険と向き合う
16歳未満の子どもたちは、SNSを通じて世界が広がるという素晴らしい体験をすることになる。一方で、リスクがあることもしっかりと伝えていきたい。
友人間のちょっとしたトラブルから、最悪の場合、犯罪に巻き込まれるケースまで危険性のバリエーションは幅広い。本人も気がつかないうちに引き込まれてしまうのが恐ろしいところ。子どもたちがSNSを始める前に、危険性を認知させる必要がある。
2025年の現在、日本では「闇バイト」などと総称される犯罪行為が広まっている。社会経験のない若年層の子どもが親の監視下を離れて、犯罪に巻き込まれる。SOSを発する前に、気づいてあげることができればいいが、そもそも子供たちは自分たちは「危険」という認識が無いケースが多い。
年齢的に、今よりも監視することは難しい状況になっている。年頃の子どもたち(16歳)は、自身のスマートフォンをもち、流行の情報収集・コミュニケーションなどを楽しむ。親はその内容について、細かく把握することは難しい。親が子どもに見ている内容を問い合わせたとき、真実を語ってくれるような信頼関係を築けているか、その辺りが重要な課題となる。できれば早く、SNS導入の段階で、親が子どもと話し合い、危険性を理解した上で活用させたい。
SNS、運営側に求められることは?
それではどういった企業を選ぶ必要があるのか。ひとつは年齢制限(16歳未満のアクセスを拒否)に関して、明確な使用規定を設けているアプリケーションを選ぶことが良いだろう。既に一部、Instagramなどは利用者登録の際に生年月日を入力しないと利用することができない。※13歳以上でないと利用不可
企業側のデメリットとしては、運営面のコストや、16歳未満のユーザー低下による広告費の減少などが考えられる。一方で、このような法律に対してポジティブな側面もある。真摯に向き合う姿勢を見せることで、ブランド価値・信頼を高めることができる点だ。私たちは、企業の取り組み方を見守り、利用するか否かを判断する必要がある。
まとめ
日本国内では現在、具体的な法案を進める動きはない。自分の身は、自分で守る必要がある。
かつて、スマートフォンは携帯電話であり、電話機だった。タブレット端末が世の中にない社会。家庭・会社、もしくは学校にパソコンがあれば、限定的に一部のSNSへの参加が可能だった。しかし、今はいつでも・どこでもデバイスを持ち運べる。個人は誰かとすぐに繋がることができる。この流れは誰にも止めることはできない。現代を生きる私たちは、子どもから完全にSNSとの関わりを断つことは難しい。コミュニケーションへの欲求は、いつの時代も常に存在する。
SNSと子どもの良好な関係は、親と子の信頼関係に繋がっている。親としてできることは、「危険」という認識をしっかりと伝えること。何か問題があったとき、子どものSOSサインにすぐに気づける環境を整えることではないでしょうか。