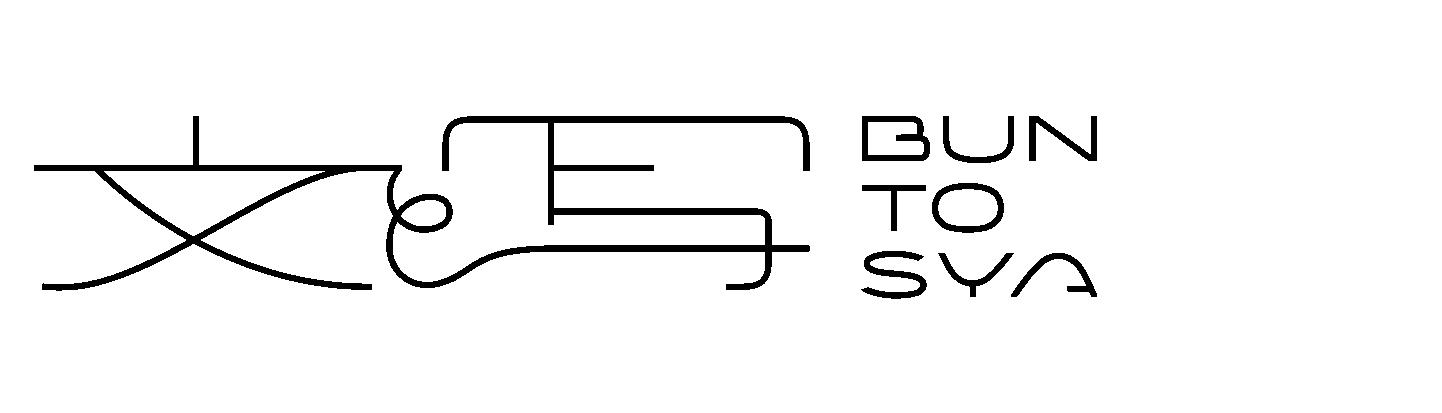生きているいう事実は、支えであった。
知らせを聞いたぼくは、会社で仕事中だった。携帯電話の画面に映し出された文字の羅列を凝視しながら、ただ固まる。祖母が亡くなった。
どうしたら良いかわからず、トイレの個室に一旦入るものの、落ち着かず。外に出ることにした。
歩きながら、ベンチを目指しているうちに涙がでてきた。大人になって久々に泣いている。後ろのポケットに入っているハンカチを取り出す。目に押しあてながら、歩く。いつも昼休みに座る、マンション裏にあるベンチに辿り着く。
気持ちの整理をつける。目を閉じて深呼吸する。大丈夫そうだ。年末には帰らない予定だった実家に、家族で帰ることにした。
「眠るように旅立った」と、父はお通夜の席で話をしてくれた。祖母は、施設でお世話になっていた。老衰だった。知らせを聞いた家族、みんなが色々な思いで、祖母の存在を振り返った。
今ごろ、天国で祖父が「おい、遅いじゃねえか」と言っているかもしれませんねと、お坊さんからお話をいただく。なんとなくその様子がハッキリと想像できたら、気持ちがスッと晴れやかに快晴となった。
嬉しいこともあるものだ。疎遠となっていた親族が集まったことで、子供たちは集まって、楽しくわいわい遊んだ。幼い頃のお葬式は、悲しみというよりはイベントだったことを思い出した。新たな別れは、繋がりを深め、交流のきっかけを与えてくれた。
火葬場で最後にお顔を拝む。お別れの際、自分は何をしてあげられただろうか。と考えた。祖母から教えられたことや、与えられたことは、ぼくの人生の指針となっている。「ありがとう」と心の中で伝えた。
祖母に教えてもらったことを、子供たちに伝える。ぼくができる、祖母への唯一の「与える」ことなのだ。その導き出した答えを胸に、これからの生活を歩むことにした。
お坊さんがつけてくれた、祖母の新しい改名には、「白雲」という字が含まれていた。透き通るような青空に雲が溶け込む様子は、祖母を連想させた。