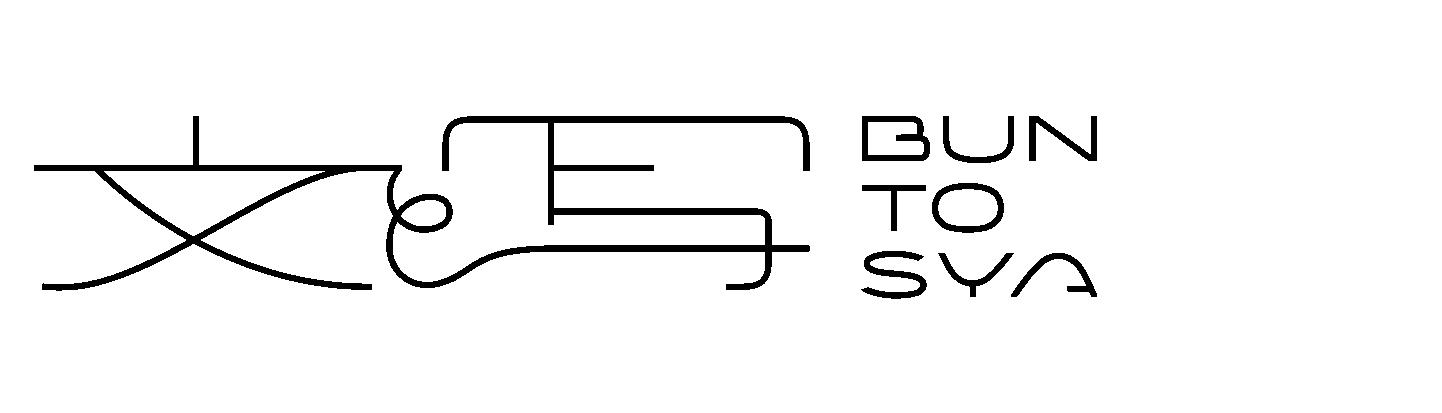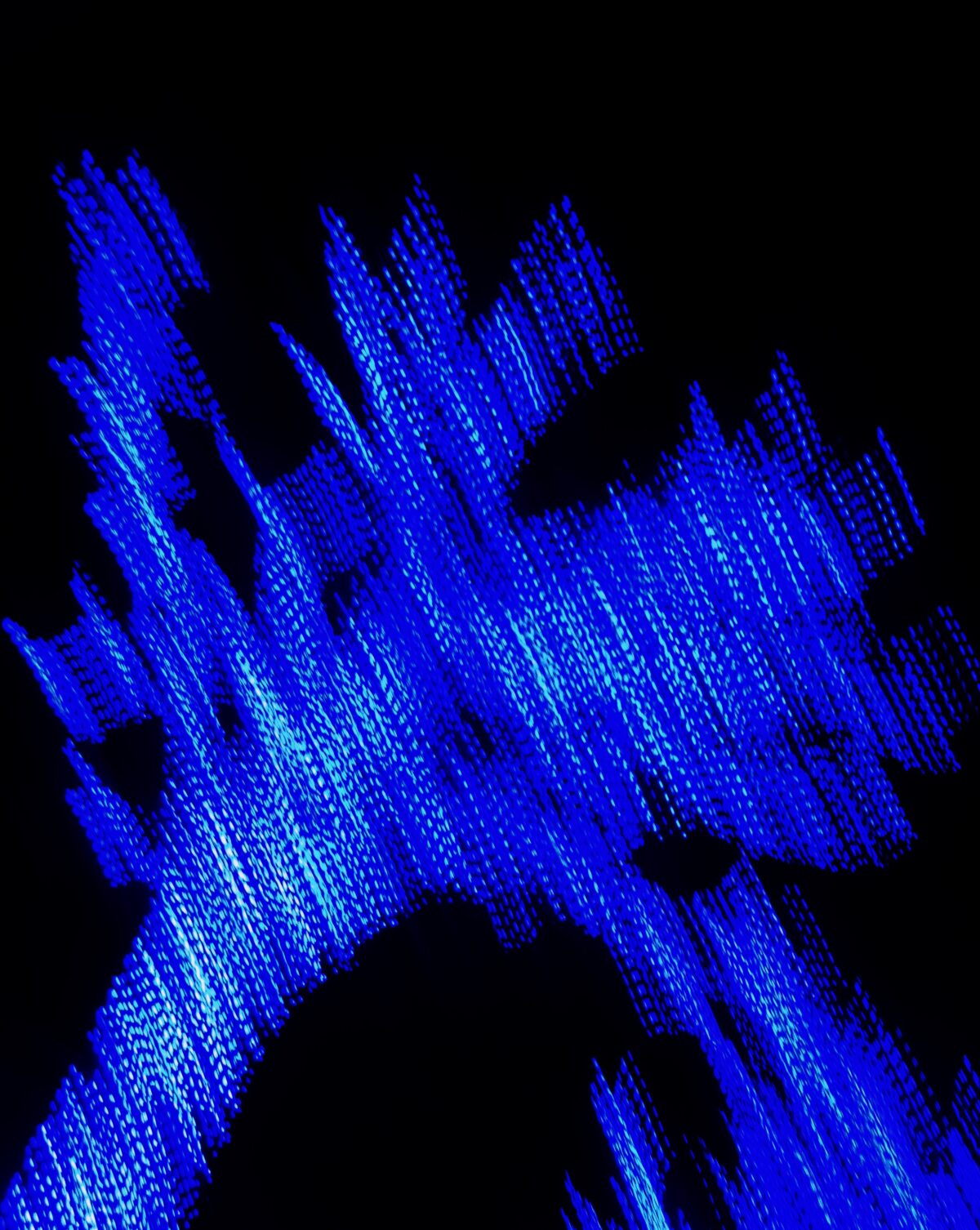庭はない、あるのは海だ。
玄関を開け、階段をくだると海が広がっていた。
中学生のわたしは、裸足のまま外に飛び出した。目の前に広がった景色は、ありえない状況だった。なぜか不思議と気にならなかった。程よく風が吹いている。いくつもの丸い波紋は、できては消えてを繰り返す。右足から、ゆっくりと水面にのせる。
やわらかい。海はやさしく足を包む。海面にゆっくりと両足をのせる。わたしは走り始めた。
走りながら、思う。中学に入り、陸上を始めた。走るのは好きだ。ただ、いつも頭の中で違和感におそわれる。母の存在。人からの評価は、いつも母が基準だ。過去の栄光はいつまでも娘である私の体を縛りつける。
追いつくことのできない、母のかがやく姿。そんな日々を繰り返していたら、気がつくと、わたしは走ることが嫌いになっていた。
海は続く。途中、雲の階段をみつけた。階段を登り、高台から水平線を眺める。歩道橋ほどの高さから眺める海。太陽のひかりが反射した水面は、美しい。高台から眺めていると、走る人影。「おーい」と聞こえるように、この世界の住人に声をかける。
呼びかけに応じたのは、女性だ。ランナーであることは筋肉のつき方でわかる。頬は赤く、すがすがしい。気になるのは、裸足で靴を履いていないこと。私とおんなじ。なぜか、彼女は自分であるような気がした。彼女は、わたしを見ると、ニコリとほほえむ。
そのまま後ろに振り返り、彼女は何かを目指して、走りだした。後ろ姿を目で追いかける。意味なんかなくていい。ただ、好きだから、走り続ける。海は風をなびかせ、そうささやく。
ああ、いつかの夢だ。夢が覚めたら、母を追うことをやめようと思った。
わたしは毎日、同じ夢をみる。