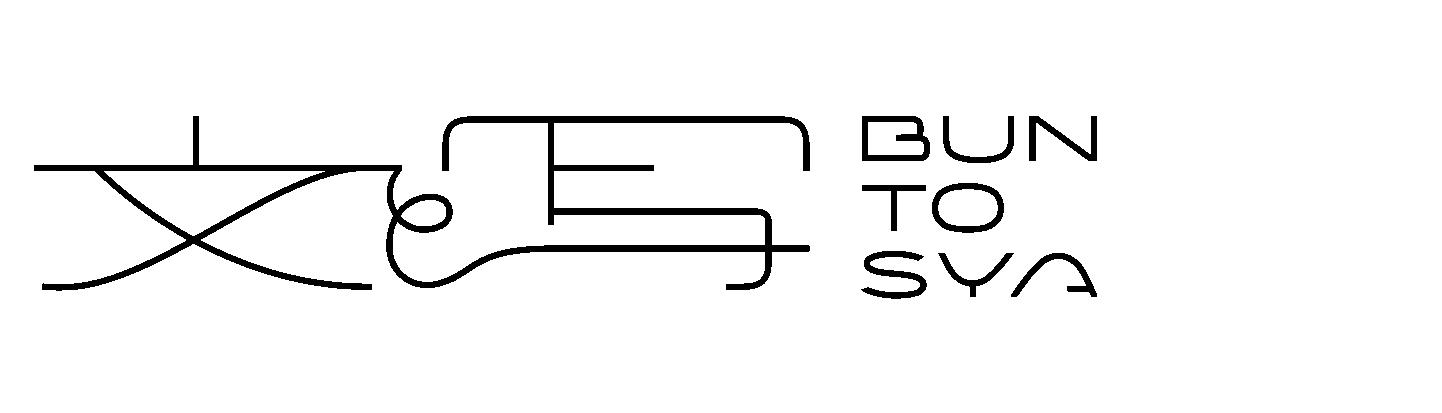旗振り役よりも、一生懸命に働いてくれる人がいる。僕のアヒルを大事に育てた、祖母の話。
中学生のぼくは、アヒルを家で育てたいと強く思った。なんの前ぶれもなく雛を家に持ち帰った。祖母は文句を言わずに、こう言った。
「アヒルかい、へぇー」
アヒルが、我が家に来た。祖母は快く承諾してくれた。新生活が始まる。この鳥は成長スピードが早い。あっという間に成長した。可愛らしい小さな黄色のぬいぐるみ。あれ、どこいった。あっという間に身体の毛は白く変化した。そして立派なクチバシを持つ、アヒルへと進化した。
アヒルの食事。細い喉に詰まらないかなと想像する。銀色のボウルに専用の餌に水を足してあげる。食べるとき、とても興奮する。感情が高まる。「クエックエッ!」と鳴きながら、僕の手を餌だと勘違いして、やたらと、つつく。「いったー。」痛みと共に、別の感情が芽生える。『恐怖』を感じるようになった。少しアヒルと距離を置く。祖母は、ぼくが距離を置いているのを知っていた。しかし、何も言わなかった。
「猫にやられるかもしれないね」
鋭い視線で灰色の塀を見ながら、祖母は言う。家の周りには野良猫がいる。アヒルを守るべく祖母は立ち上がる。裏庭に竹で骨組みを作り、緑色のネットでアヒルを覆った。猫からアヒルを守る作成だ。猫は何度かやってきたが、知らん顔して歩いて行くだけだった。作戦は成功だった。そのとき、祖母のアヒルへの愛情を感じた。
お散歩の時間。運動不足にならないように、歩かせる。網に覆われた場所からアヒルを出し入れする。アヒルを抱っこして、外へ出す。
「よっこらしょいとぉー!」
祖母がアヒルを柵の上まで持ち上げる。当然、網から出そうとするとアヒルはバタバタと足を振り回して暴れた。地面に抜けた毛が落ちる。その様子をただじっと見守る。その頃、ぼくのアヒル恐怖症は頂点に達していて、抱っこなど到底できるものではなく、すべてを祖母に任せた。アヒルは庭で自由時間を与えられる間、自由に歩いた。ひょこひょこ。祖母の後をひょこひょこひょこ。おしりを左右に振りながら、母を追いかける。
そんな暮らしも終わりを迎える。突然、アヒルは旅立った。祖母は空を見つめていた。
「アヒルを飼ったのは、初めてだったよ」
中学生のぼくが突然、アヒルを連れてきた。祖母が育ててくれたアヒル。田舎ぐらしで庭があれば飼えるってもんじゃない。祖母の愛があってこそだ。命を育てることは、愛情が必要だ。